近年、飲食業界は未曾有の変革期にあります。コロナ禍以降、経営環境は激変し、店舗側も「売上拡大」や「経営効率化」への関心を高めています。こうした背景の中、飲食店向けのサポート事業を展開する企業にとって、営業活動の在り方も見直すべきフェーズに入っています。
特に注目すべきは、ウェビナーを活用した営業手法です。従来のテレアポや訪問営業ではリーチできなかった層にも効果的にアプローチでき、かつ専門性のアピールにもつながります。本記事では、飲食店向けサポート事業を展開している経営者向けに、ウェビナーを軸とした営業戦略の構築方法を詳しく解説していきます。
なぜ今、ウェビナー営業が飲食店向け事業にフィットするのか?
飲食店経営者は「忙しい」「現場が優先」「営業に対して懐疑的」という特徴を持っています。こうした層に従来の営業手法はなかなか刺さりません。そこで効果を発揮するのが、“役に立つ情報を無料で届ける”という姿勢を示せるウェビナーなのです。
特に次のようなポイントが、飲食店向けサポート事業と相性抜群です。
- 時間と場所を選ばず参加できる(店舗経営者の負担が少ない)
- 教育型営業として機能する(サービスの背景や価値をしっかり伝えられる)
- 見込み客のリストが自然に獲得できる(参加者情報=リード)
ウェビナー営業の成功事例(飲食店向け事業編)
実際に、POSシステムや予約管理ツールを提供する企業が、「飲食店経営のためのDXセミナー」を開催した結果、100名以上のオーナーが参加し、その後の個別面談率が30%を超えたというケースがあります。
この事例では、以下のような工夫が功を奏しました。
- テーマ設定を現場目線にする:「人手不足でも売上を上げる店の裏側」など
- 参加特典を設定:無料診断レポートや限定動画を提供
- ウェビナー後のフォローを徹底:アンケートと合わせて個別相談誘導
飲食店向けウェビナー営業の進め方ステップ
ステップ1:明確なターゲットを設定する
居酒屋、カフェ、チェーン店、個人店など、どの層に響くかを見極めましょう。全てにアプローチするのではなく、「個人経営の焼鳥屋を3店舗以上展開している人」など、絞り込んだほうが成果が出やすいです。
ステップ2:ニーズに沿ったテーマを設計
情報発信のテーマがズレていては、誰も参加しません。以下は鉄板テーマの例です:
- 「原価率30%台でも黒字化する飲食店の作り方」
- 「スタッフの定着率が2倍になった、現場マネジメント術」
- 「キャッシュレス化で売上が20%伸びた店のリアル」
ステップ3:告知と集客の導線を整える
ウェビナーは開催するだけでは意味がありません。SNS、メルマガ、LINE、業界団体との連携など、複数チャネルで訴求し、リマインドも含めてフォローする仕組みが大事です。
ステップ4:当日の運営とプレゼン設計
「売り込み」ではなく、「価値提供」を前提にしたプレゼン構成が鉄則です。飲食店経営者は売られることに敏感なので、あくまで“学び”を中心に構成し、最後にさりげなくサービスへの誘導を行いましょう。
ウェビナー後の”個別アプローチ”が成約のカギ
ウェビナーの本当の目的は「その後の1対1の商談」です。以下のようなアクションを確実に設計しておくことで、成約率が大幅にアップします。
- アンケートで課題感をヒアリング
- 個別相談会への誘導(無料)
- スモールスタート提案(お試し導入など)
飲食店向けサポート事業者にとってのウェビナー活用の未来
ウェビナーは、単なる”セミナー”ではなく、信頼構築ツールであり、ブランド構築手段でもあります。実績を積み重ねることで、「この分野の専門家」としての認知が広がり、指名での相談や提携依頼が増える土壌になります。
また、録画コンテンツをアーカイブとして活用すれば、YouTubeなどでのSEOにも貢献し、資産型の営業導線としても機能します。
まとめ:今こそ「提供者から教育者」へとシフトを
飲食店向けのサポート事業は、現場理解と専門性が鍵になります。だからこそ、“教える”ことを通じて価値を届けるウェビナー営業は、もっとも費用対効果の高い手法の一つです。
経営者として「営業部門の再構築」を検討されているのであれば、ぜひこのウェビナー営業を一つの柱として取り入れてみてください。数年後には、“見込み顧客はウェビナー経由で取る”が常識になっている可能性すらあります。


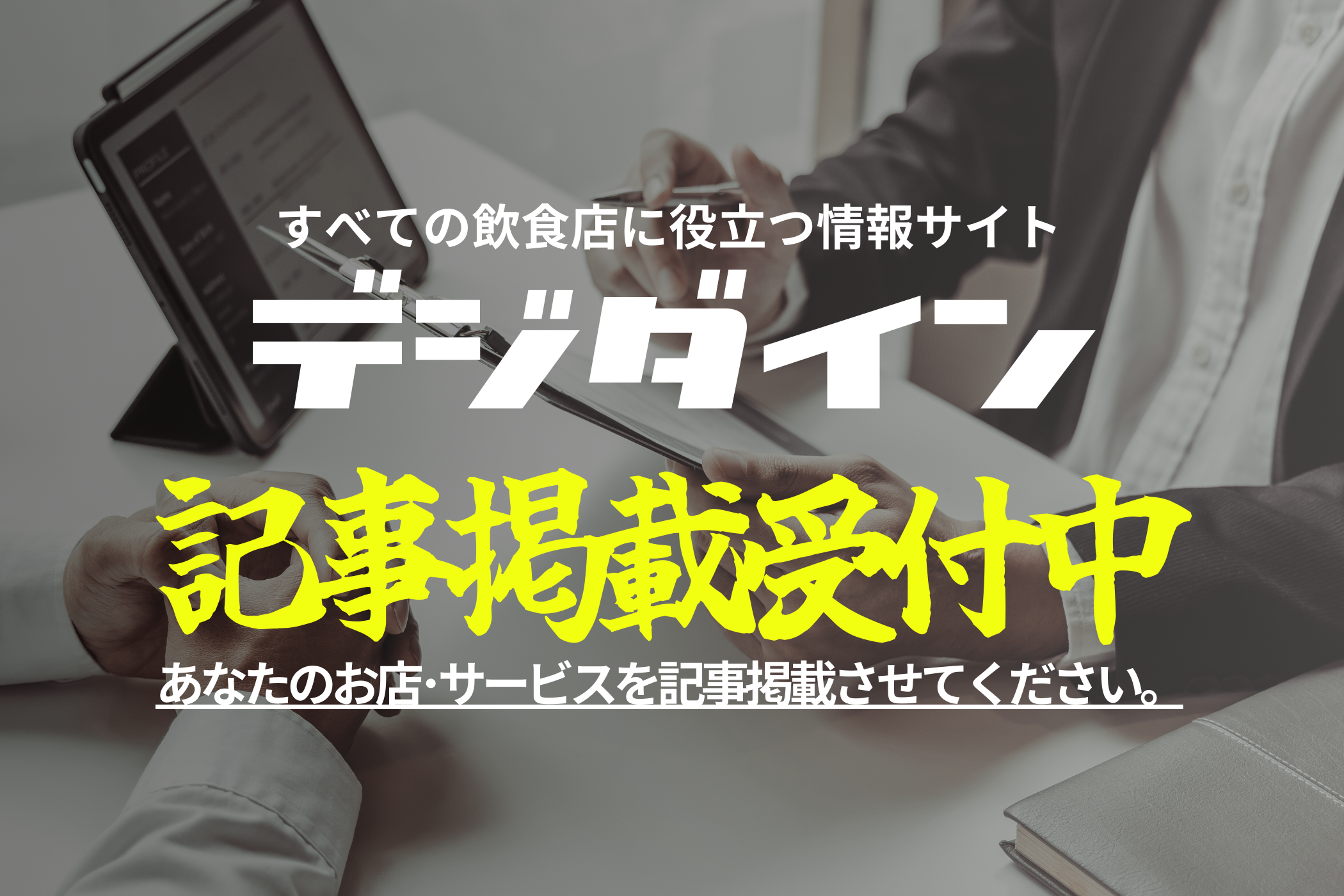
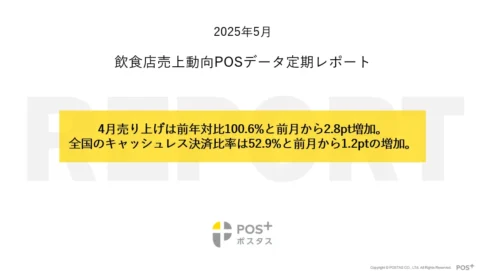




コメントを残す