飲食店業界を取り巻く環境は、ここ数年で劇的に変化しています。コロナ禍による打撃からの回復、DX(デジタルトランスフォーメーション)推進、そして人手不足への対応など、飲食店はこれまで以上に多様な課題に直面しています。こうした背景の中で、飲食店を支援するサポート事業の重要性も増しており、それに伴って営業とマーケティングの在り方も再定義されつつあります。
今回は、飲食店向けサポート事業を展開している企業にとって極めて重要なテーマである、**「インサイドセールスとマーケティングの連携」**について解説します。リード獲得から商談化、契約までのプロセスをスムーズにし、限られたリソースで成果を最大化するためのヒントをご提供します。
なぜ「インサイドセールス」と「マーケティング」の連携が不可欠なのか?
従来の営業手法では、営業担当者が直接訪問し、課題をヒアリングして提案するという「アウトサイドセールス」が中心でした。しかし、コロナ禍以降、非対面での営業活動の必要性が高まり、「インサイドセールス」の重要性が急速に増しています。
特に、飲食店サポート事業においては、検討期間が短く、ニーズが急激に立ち上がるケースが多いため、スピーディーかつ的確なアプローチが求められます。
このような業態では、インサイドセールスとマーケティングが連携することで以下のようなメリットが得られます。
- ターゲットの行動履歴に基づくタイムリーなアプローチ
- 顧客ニーズに合わせたコンテンツの提供
- リードの精度向上と歩留まりの改善
- 商談化率の上昇による営業効率の最大化
飲食店向けサポート事業におけるよくある課題
飲食店向けのサービスは多岐にわたり、POSレジ、モバイルオーダー、予約管理、集客支援、人材紹介などが挙げられます。これらのサービスは、緊急性のあるニーズと長期的な投資判断のバランスが難しく、**「とりあえず資料請求したけど判断できない」**というリードが非常に多いのが実情です。
この段階でインサイドセールスとマーケティングの連携がうまくいっていないと、以下のような問題が起きがちです。
- リードが温まらないまま放置される
- メールマガジンの内容が一方通行で効果が薄い
- 営業とマーケティングのKPIがバラバラで連携が取れない
- 資料請求やセミナー参加者が商談につながらない
成果を生む連携のポイントとは?
インサイドセールスとマーケティングの連携を実現するためには、以下の3つのポイントを押さえることが重要です。
1. 共通のKPI設計
マーケティングチームは「リード数」、インサイドセールスは「商談化率」など、別々の指標を追いかけていては連携が機能しません。「MQL(Marketing Qualified Lead)からSQL(Sales Qualified Lead)への転換率」などの共通指標を設定し、部門間の成功定義を一致させることが第一歩です。
2. スコアリングとナーチャリングの仕組み化
飲食店の経営者は日々忙しく、長文の提案資料を読む時間もありません。リードの行動履歴(メール開封、Web閲覧、資料ダウンロードなど)を分析し、ホットリードに優先して接触する体制を整えることが重要です。さらに、まだ商談タイミングではないリードには、継続的に有益なコンテンツ(事例・業界ニュース・制度情報など)を提供し、信頼関係を構築しておくことが欠かせません。
3. データ基盤とCRMの統一
マーケティングツール(MA)と営業支援ツール(SFA/CRM)が連携していないと、リードの情報が分断され、適切なアプローチが困難になります。HubSpot、Salesforce、カスタマーリングスなどの統合ツールを活用し、ワンソース・ワンデータの体制を構築しましょう。
成功事例:飲食店向け求人支援サービスの場合
ある飲食店向け求人マッチングサービスでは、マーケティング部門が月間100件以上のリードを獲得していたにもかかわらず、商談化率はわずか5%以下という課題を抱えていました。
そこで、以下のアクションを実施:
- インサイドセールスを新設し、スクリプトとリード管理シートを整備
- MAツールを導入し、メール開封率とWeb行動データを可視化
- 業種別・規模別にセグメントを切り、カスタムコンテンツを配信
- 月1回の「マーケ×セールス連携会議」を実施
結果、商談化率は25%に向上し、半年で売上も約2.3倍に拡大しました。
まとめ:インサイドセールスとマーケティングは“ワンチーム”で動け
飲食店向けサポート事業は、緊急度の高い案件と、じっくり検討が必要な案件が混在する難しい業態です。その中で成果を出すには、インサイドセールスとマーケティングの密接な連携が不可欠です。
リードを数としてカウントするのではなく、「どう育てて、どう届けるか」に注目しましょう。データに基づいた行動と、顧客理解をベースとしたアプローチが、競合との差別化と成長のカギとなります。
今こそ、自社のインサイドセールスとマーケティングの連携体制を見直すチャンスです。


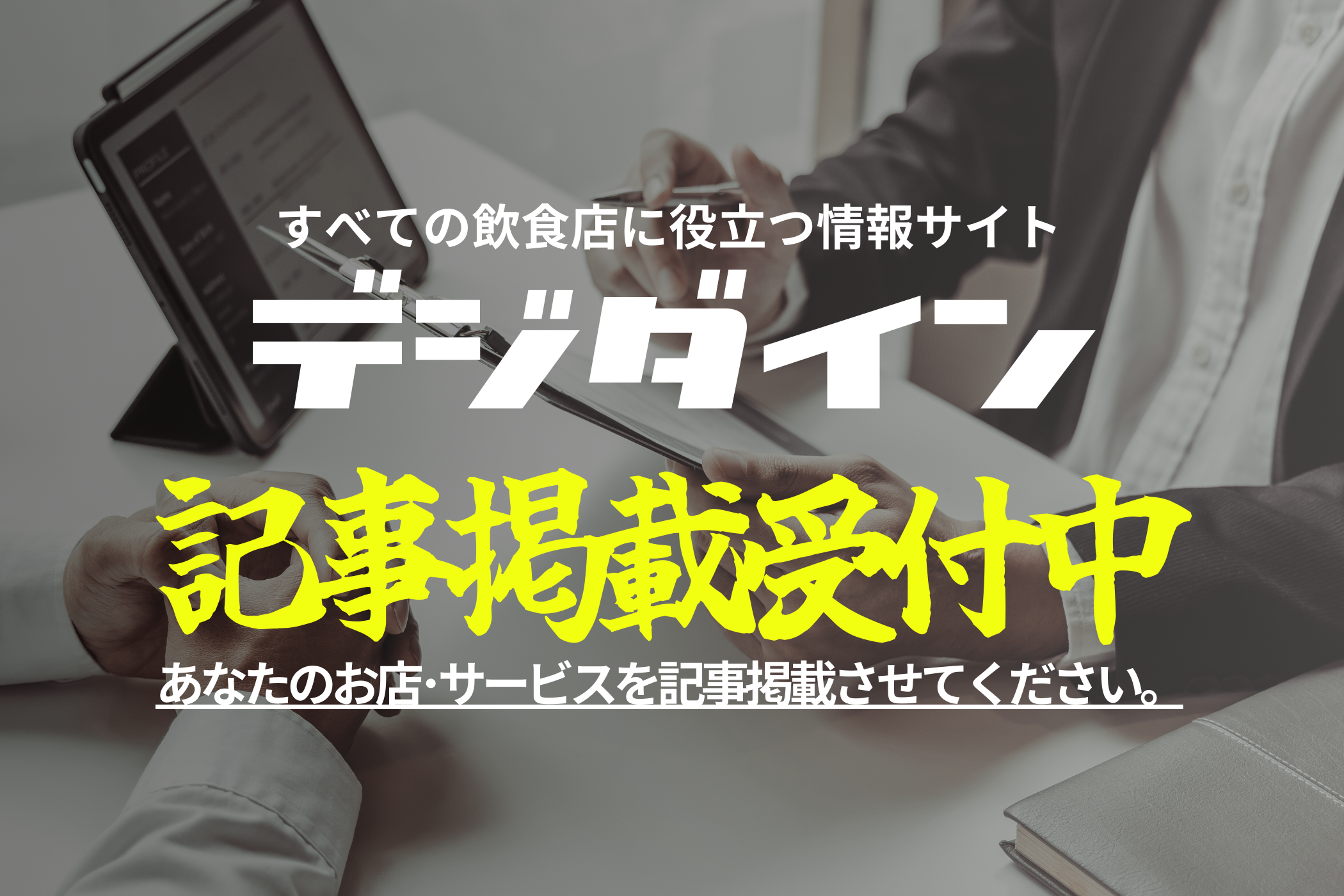
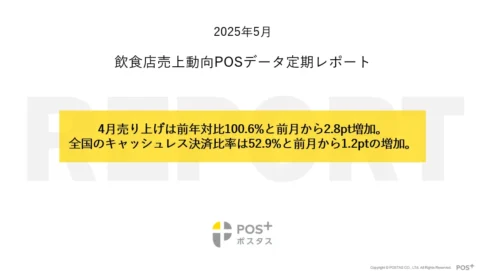




コメントを残す