飲食店業界は、近年ますます複雑化・多様化しています。デジタル化、インバウンド需要、原価高騰、人材不足など、課題は山積みです。こうした背景から、飲食店向けのサポート事業は今、大きな需要を抱える分野のひとつとして注目を集めています。
しかし、どれだけ魅力的なサービスを用意しても、それを適切に届け、成果を上げる営業体制がなければ事業は伸びません。そこで今、多くの企業が取り入れ始めているのが「インサイドセールス」です。
本記事では、飲食店向けサポート事業を展開する企業経営者の方向けに、インサイドセールスのKPI設計と成果測定のポイントについて解説していきます。
なぜ今「インサイドセールス」なのか?
インサイドセールスとは、電話やメール、SNS、ウェビナーなどを活用し、非対面で見込み顧客にアプローチし、商談化につなげる営業手法です。
飲食店は多忙な業態であり、直接訪問を嫌う経営者も多い中で、オンラインでの関係構築が可能なインサイドセールスは非常に有効です。また、営業コストを削減しながら、接触機会を増やせる点も大きなメリットです。
インサイドセールスにおけるKPI設定の重要性
インサイドセールスの導入は「属人性」を排除し、再現性のある営業組織を作る第一歩です。ですが、その効果を正しく測定するには、明確なKPI(重要業績評価指標)の設定が不可欠です。
特に飲食店向けサポート事業の場合、商談化までのリードタイムが短く、決裁権者への到達率も重要な要素となるため、KPIを設定する際には次のような指標が有効です。
飲食店向けインサイドセールスで押さえるべきKPI5選
1. リード獲得件数(SQL・MQL)
- MQL(Marketing Qualified Lead):資料請求や問い合わせをした見込み顧客
- SQL(Sales Qualified Lead):インサイドセールスによって「商談化可能」と判断されたリード
飲食店の場合、MQLの段階でかなり温度感が高いことも多く、いかにSQLへと転換させるかが勝負です。
2. コンタクト率
「架電・メール送信数」から「実際に接触できた数(会話や返信があった数)」を割ったもの。飲食店は電話に出られないタイミングも多いため、曜日・時間帯の最適化による改善余地が大きいポイントです。
3. アポイント獲得率
接触したリードの中で、実際に商談設定ができた割合。トークスクリプトの洗練、サービス訴求の明確化が直結する部分です。
4. 商談化率(パイプライン化率)
アポイントの中でも「課題を共有し、提案フェーズへ進めた案件」の比率。ここからがフィールドセールスやカスタマーサクセスへのパスになる重要KPIです。
5. 受注率と平均受注単価
最終成果を測る上で不可欠なのが**「受注率」と「平均受注単価」。特に飲食店は少額から導入できるSaaSや販促支援が多いため、単価を上げるにはアップセルや複数店舗展開の導入戦略**がポイントになります。
成果を高めるためのKPI分析の視点
KPIは設定するだけでは意味がありません。週次・月次でボトルネック分析→仮説→改善施策→再実行のサイクルを回すことが成功の鍵です。
例:
- コンタクト率が低い → 曜日・時間帯を変更、架電リストの精度を見直す
- アポ率が低い → スクリプトの見直し、成功事例の横展開
- 商談化率が低い → 顧客課題の深掘り不足、ニーズヒアリング力の強化
飲食店向けサポート事業における「KPIとLTV」の関係性
飲食店は継続契約や紹介が多い業界です。インサイドセールスのKPI改善によって顧客獲得単価(CAC)を下げ、LTV(顧客生涯価値)を最大化することが、事業全体の利益構造を改善します。
KPI設計 → 改善 → CAC抑制 → LTV向上 → 利益率の向上
この流れをいかに作れるかが、飲食店向けサポート事業における**「インサイドセールス部門の成功の鍵」**となるのです。
まとめ:KPIを「仕組み化」し、再現性ある営業体制を
飲食店向けのサポート事業は、「個人プレイでは伸びにくい市場」です。再現性のある営業体制を築くために、インサイドセールスのKPIを明確に設計・運用することが不可欠です。
特に経営者の立場であれば、「KPIの数字」だけでなく「その先のLTV」「再現性」「営業投資効率」などの視点を持つことで、より戦略的な事業拡大が可能になります。
営業は感覚ではなく、科学です。
インサイドセールスをデータドリブンに活用し、飲食業界の未来を支える存在になっていきましょう。


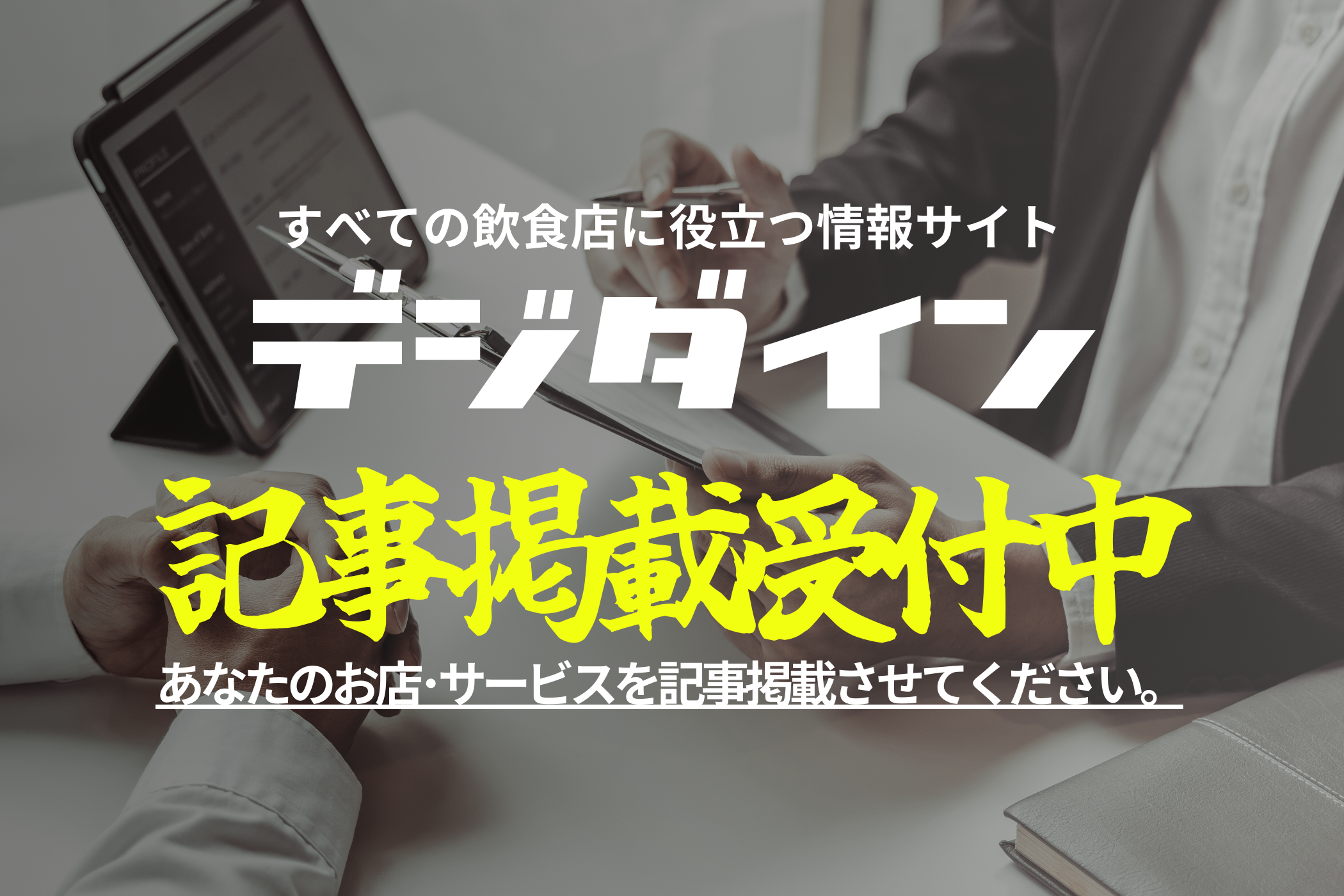
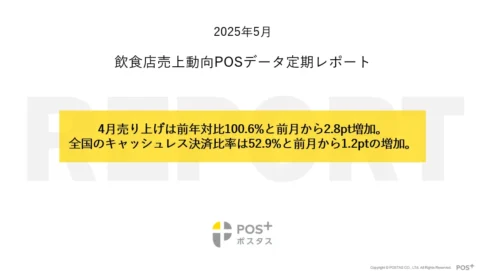




コメントを残す