飲食業界は今、大きな変革期を迎えています。コロナ禍を経て経営の在り方が変化し、デジタル導入や効率化、さらには“人手不足”や“離職率の高さ”など、課題が山積しています。そんな中、飲食店向けの支援サービスを展開している企業にとって、いかにして多くの店舗にリーチし、提案を届け、商談につなげるかがビジネスの鍵を握っています。
その中核を担うのが「インサイドセールス」です。本記事では、飲食店向けサポート事業における成果を出すインサイドセールスのトークスクリプトの作り方について、具体的かつ実践的に解説していきます。
■ なぜインサイドセールスが飲食業界に有効なのか?
飲食店経営者は、とにかく忙しい。営業時間中は接客と現場対応に追われ、休憩時間も仕入れや発注、シフト管理などで多忙を極めます。そのため、いきなり飛び込み営業や無計画な電話営業をかけても、「今忙しい」「後にして」と断られるのがオチです。
ここで重要になるのが、“興味喚起→関心形成→課題顕在化→商談化”というインサイドセールスのファネル型アプローチです。
電話一本で売るのではなく、「課題に気づいてもらい、興味を持ってもらい、次のステップ(アポ取得や資料送付)につなげる」ことが目的です。
■ トークスクリプト作成の3ステップ
1. 【導入】興味喚起を仕込んだ一言
冒頭の15秒が命。飲食店経営者の“足を止めてもらう”ことに全力を注ぎましょう。
例:
「〇〇エリアで飲食店様向けに【人手不足解消支援】をしている◯◯と申します。1分だけ、今話題の補助金活用についてだけお伝えしてもよろしいでしょうか?」
→「補助金」や「コスト削減」「人手不足」など、経営課題に直結した“キーワード”を先に提示するのがポイントです。
2. 【本題】共感+実績+問いかけ
ここでは、共感・実績・ヒアリングを3点セットで展開します。
例:
「多くの飲食店様が、今“人材確保”や“離職防止”に悩まれていて、実は私たちもここ半年で〇〇件のお店をサポートしてきました。
ちなみに、貴店でも“採用”や“教育”で課題を感じられていたりしますか?」
→「共感」で壁を下げ、「実績」で信頼を取り、「問いかけ」で相手の状況を引き出します。
3. 【終盤】選択肢提示型クロージング
いきなり「アポいいですか?」はNG。相手に主導権を渡しつつ、行動を提案する形がベストです。
例:
「このような取り組みに少しでも興味を持っていただけたら、
(1)5分のオンライン説明
(2)事例資料のご送付
どちらがご都合よさそうでしょうか?」
→「Yes/No」ではなく「AかBか」の選択肢を与えることで、自然な流れで次のステップに進めます。
■ スクリプト成功のための補足ポイント
- 情報は詰め込みすぎない:トーク時間は1〜2分以内に。あくまで“興味喚起”がゴール。
- 業種・立地別にテンプレを複数用意:個人経営の居酒屋とチェーンのカフェでは訴求点が全く異なります。
- スクリプトは台本ではなく“対話の設計図”:覚えようとせず、流れの「意図」を理解することが大切です。
- 反論対応も準備する:よくある「今忙しい」「予算がない」「社長不在」などへの返しも用意しましょう。
■ 飲食店支援事業の未来は“営業力”にかかっている
デジタルサービスや業務改善ツール、求人支援や省人化ソリューションなど、飲食店向けの支援ビジネスは年々増加しています。しかし、その数が増えれば増えるほど、「何をしてくれる会社なのか」「どんな価値があるのか」を明確に伝えられないと、埋もれてしまいます。
だからこそ、“営業力=伝える力”が今後ますます重要になるのです。
■ まとめ:成果を出すには、現場感を理解したスクリプト設計を
インサイドセールスは、ただの電話営業ではありません。戦略的に相手の心理とニーズに寄り添いながら、段階的に関係性を構築していく“マーケティング型営業”です。
飲食店向けサポート事業を展開する企業様にとって、こうしたアプローチは競合優位性の差別化にもつながります。
一度きりの営業で終わらず、“また連絡してもいいですか?”と思わせる関係性を作ることが、持続的な売上と信頼につながります。
今こそ、「トークスクリプト」という武器を本気で見直すタイミングです。


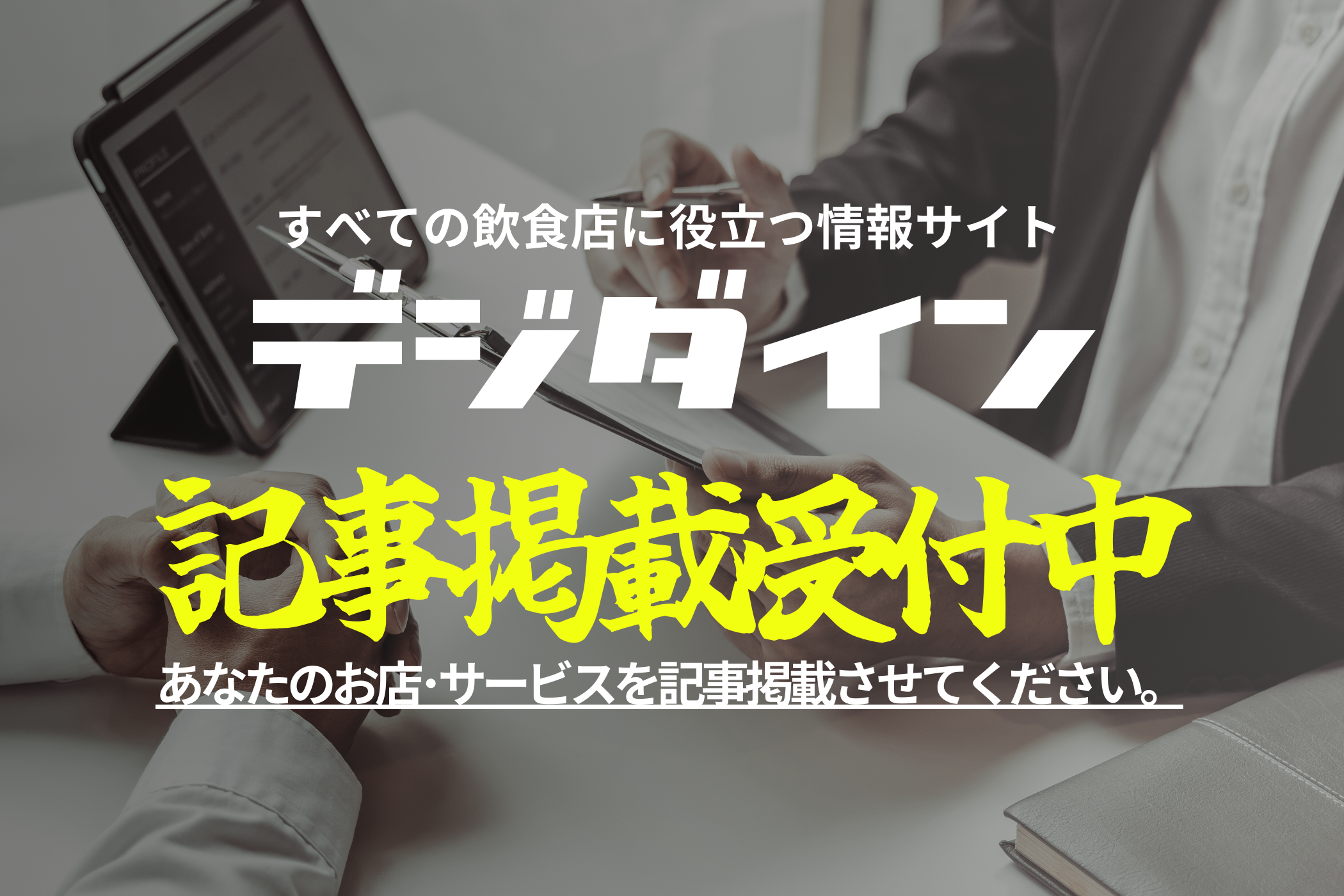
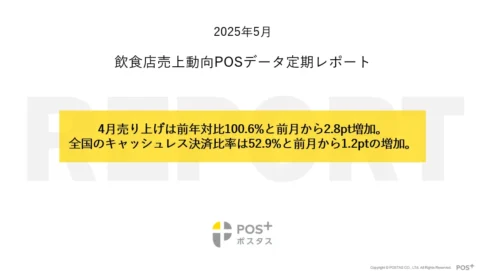




コメントを残す