飲食店を対象にサービスを提供している企業経営者にとって、**「営業体制の最適化」**は成長に直結する課題です。特に、インサイドセールスとフィールドセールスの違いを理解し、それぞれの役割を正しく活用することが、競合との差別化とスケーラブルな営業体制の構築において欠かせません。
本記事では、飲食店向けサポート事業を展開する企業が知っておくべき、インサイドセールスとフィールドセールスの違いと、それぞれの効果的な活用方法について詳しく解説します。
インサイドセールスとは?──飲食店との接点を効率的に作る
インサイドセールスとは、電話・メール・オンライン会議ツールを活用して顧客と非対面で接点を持ち、商談機会を創出・育成していく営業手法です。
飲食店向けサービスにおいては、以下のような場面で活躍します。
- 新規開業予定の店舗へのアプローチ
- 過去に問い合わせのあった店舗への再提案
- 資料請求やウェビナー参加者へのフォローアップ
- 営業エリア外の店舗とのコミュニケーション
メリットは、1人あたりが対応できる顧客数が多く、営業効率が高いこと。また、CRMやMAツールとの連携で、リードの情報を蓄積・分析しやすく、ナーチャリング(育成)に強みを持ちます。
フィールドセールスとは?──対面の信頼構築とクロージングに強い
フィールドセールスは、実際に顧客のもとに訪問し、対面で商談や提案を行う営業スタイルです。
飲食業界は、経営者や店長との「信頼関係」が商談の成否を大きく左右するため、以下のような場面では特にフィールドセールスが効果を発揮します。
- 高単価の導入商材(POSレジ、厨房機器等)の提案
- 店舗の現場を確認しないと正確な提案ができないサービス
- 地域密着型で競合の多いエリアにおける信頼獲得
- 継続的な導入支援やアフターフォローの場面
対面の強みは、店舗の雰囲気や経営者の人柄を肌で感じながら、カスタマイズされた提案ができること。価格以上の価値を「空気感」や「安心感」で訴求できます。
違いだけでなく“連携”が重要──ハイブリッド型の営業戦略
重要なのは、「どちらが良いか」ではなく、インサイドセールスとフィールドセールスをどう組み合わせるかです。
典型的なハイブリッド型の流れ
- インサイドセールスがリード(見込み顧客)を獲得・育成
- 商談の確度が高まったタイミングで、フィールドセールスが訪問・クロージング
- 導入後のアフターフォローは再びインサイドセールスが担当
この流れにより、営業コストを最小限に抑えながら、受注率を最大化することが可能です。
飲食店サポート事業では、開業ラッシュや季節ごとのニーズ変化があるため、スピード感と個別対応の両立が求められます。その意味でも、分業と連携の体制構築が鍵になります。
飲食店向けサポート企業が陥りがちな失敗
【1】すべてをフィールドセールスで対応してしまう
訪問コストが高くなり、1人あたりの対応顧客数が限界に。リードの育成が後回しになりがち。
【2】インサイドセールスに任せきりでクロージング力が不足
受注直前の「最後のひと押し」ができず、他社に流れてしまうケースが発生。
【3】CRMを活用せず、営業プロセスが属人化
「誰がどこまで対応したか」が見えず、リードが抜け落ちるリスクが高まる。
今すぐ始めたい「営業体制最適化」の3ステップ
- ターゲット層ごとに営業フローを設計する
例:個人店開業→インサイド主導、中規模チェーン→ハイブリッド対応 など。 - 営業支援ツールの導入を検討する
CRM、SFA、MAツールなど。Googleスプレッドシートからの脱却を。 - 営業メンバーの役割と評価制度を分ける
インサイド=リード獲得・育成/フィールド=商談化・成約…と明確化。
まとめ:営業体制の進化が事業成長のカギ
飲食店向けのサポート事業は、今後も高いニーズが期待される一方、競合も増加の一途です。だからこそ、営業手法のアップデートは企業経営者にとって最優先課題の一つです。
インサイドセールスとフィールドセールスの違いを理解し、それぞれの強みを活かした営業体制を構築することで、貴社の提案はより多くの飲食店に届き、継続的な成長が可能になります。


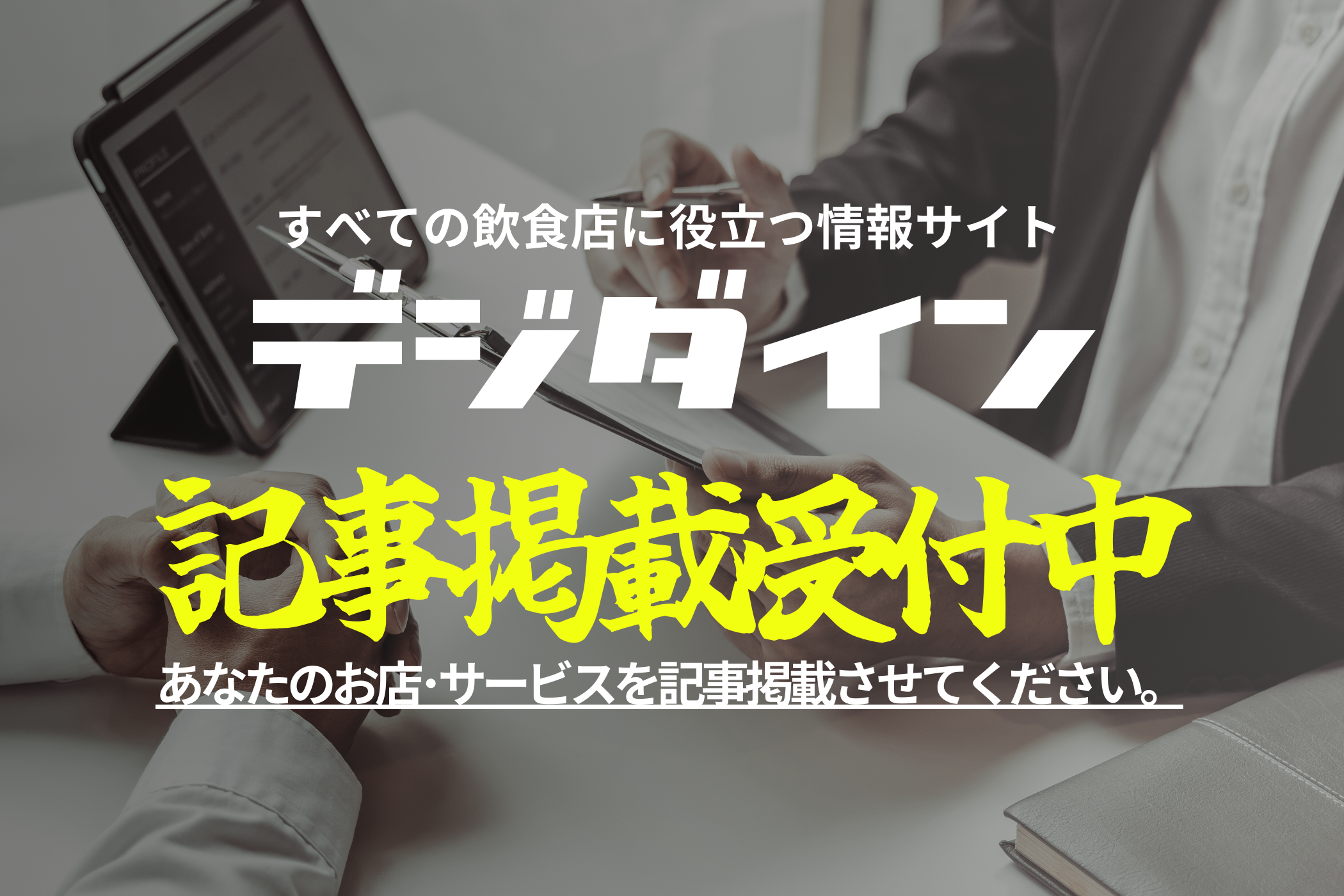
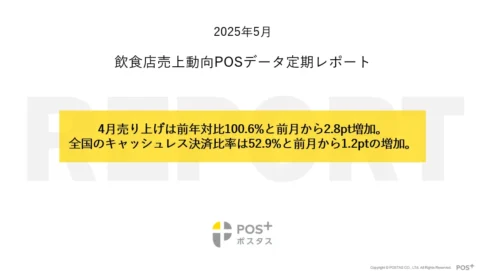




コメントを残す