飲食業界を支援するサービスは、今や多岐に渡ります。予約管理、POSレジ、仕入れ管理、デジタルマーケティング、人材採用支援など、飲食店向けのBtoBサービスは年々増加しています。
一方で、こうした飲食店向けサポート事業を展開している企業が抱える共通の課題は、「営業効率の低さ」と「アプローチの限界」です。飛び込み営業や展示会頼りでは、人的コストが膨らみ、結果としてROIが合わないという声も少なくありません。
このような課題に対し、近年注目されているのが**「インサイドセールス」**の導入です。
インサイドセールスとは?なぜ飲食店向けサービスに有効なのか
インサイドセールスとは、電話・メール・オンライン会議などを用いて、訪問をせずに顧客と接点を持つ営業手法です。従来の外勤営業(フィールドセールス)とは異なり、効率的にリード(見込み顧客)を育成し、商談化することに重きを置きます。
では、なぜこの手法が飲食店向けBtoB事業に特に効果的なのでしょうか?
1. 飲食店の営業時間にマッチする
飲食店の担当者は日中のアイドルタイム(14:00~17:00など)であれば、比較的話がしやすく、オンラインでの接点も取りやすい時間帯です。インサイドセールスなら、その短いタイミングを狙って効率的にアプローチ可能です。
2. エリア制限がなく、全国対応が可能
都内だけでなく地方の飲食店とも関係性を築けるため、事業のスケーラビリティが圧倒的に高くなります。
3. コストを抑えながらPDCAを高速回転できる
フィールドセールスと比べて1件あたりのコストが低く、データを活用した改善も可能。これは、スタートアップや中小企業にとって大きな武器になります。
インサイドセールスの導入ステップ(飲食店向けサポート企業向け)
では、実際に導入するには何から始めればいいのでしょうか?ここでは5つのステップで基本を押さえましょう。
ステップ1:ターゲット飲食店の明確化
「全ての飲食店」はターゲットではありません。例えば、居酒屋チェーン・ラーメン専門店・ベーカリーなど、業態ごとのペルソナを設計し、どんな課題を持っているかを深堀りします。
ステップ2:リード獲得の仕組みづくり
SNS広告・SEO・展示会などで獲得したリードを、CRMやSFAで管理。営業が属人化しない仕組みを構築しましょう。資料請求やウェビナー登録など、ナーチャリング導線の整備も忘れずに。
ステップ3:スクリプトとトークの設計
飲食店は「電話営業嫌い」なケースも多いため、相手に寄り添ったスクリプト設計が肝心です。「忙しいところ失礼します」から始め、「実は近隣の●●店さんでも導入されてまして…」など、信頼関係を築ける情報設計が求められます。
ステップ4:インサイドセールスとフィールドセールスの分業
インサイドで商談化したリードは、フィールドチームが訪問やデモを実施する流れが理想です。これにより、リソースの無駄打ちを削減し、クロージングの精度が上がります。
ステップ5:KPIとフィードバックループの運用
「商談化率」「受注率」「1リードあたりコスト」などのKPIを数値で可視化。毎週の定例でチーム内で共有し、トーク改善や顧客理解を深める場とすることで、再現性のある営業体制が構築されます。
インサイドセールス導入後の成功事例(仮想)
ある予約管理システムを提供している企業では、インサイドセールス部隊を立ち上げ、最初は3名体制でスタート。1ヶ月で1日20件の架電を行い、月間10件の商談を創出。そのうち3件が新規受注につながり、従来の訪問営業に比べて5倍の効率で受注獲得できました。
また、導入から半年後には、地方の個人経営の飲食店にもリーチ可能になり、販路が都心中心から全国へと広がる成果を実現しています。
まとめ:今こそ「飲食店向けサポート事業」こそ、インサイドセールスを
飲食業界を取り巻く環境は日々変化しています。人手不足、原価高騰、集客難…。そうした中で、支援サービスを提供する企業は、本当に「必要な人に、必要なタイミングで届く営業活動」が求められています。
インサイドセールスは、単なる効率化手段ではなく、“選ばれる企業”になるための戦略的な営業設計でもあります。
「営業の勝ちパターンがまだ確立できていない」「営業組織を効率化したい」──そう思ったタイミングが、インサイドセールスの導入チャンスです。
飲食店を支えるあなたの事業に、もう一段上の成長を。


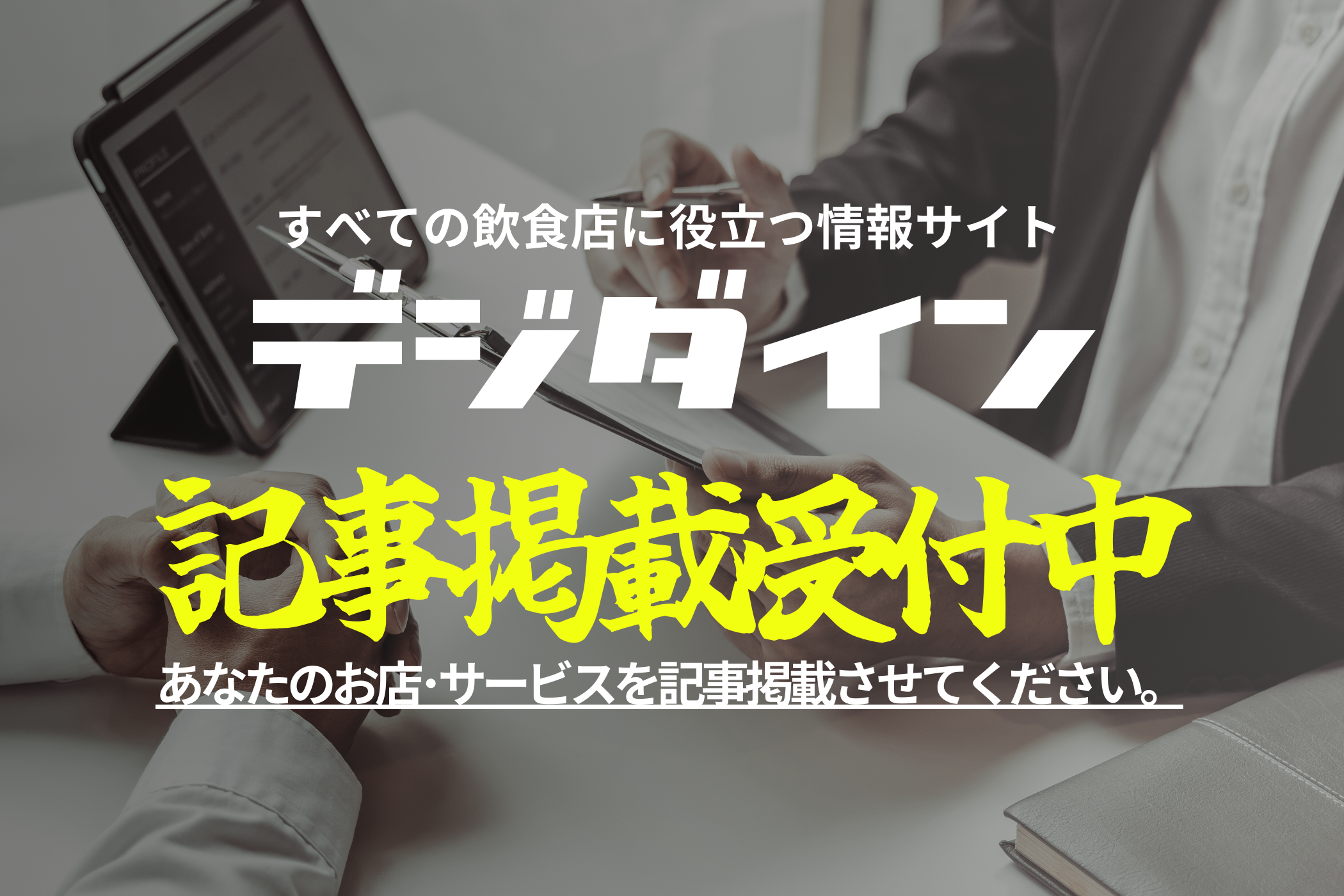
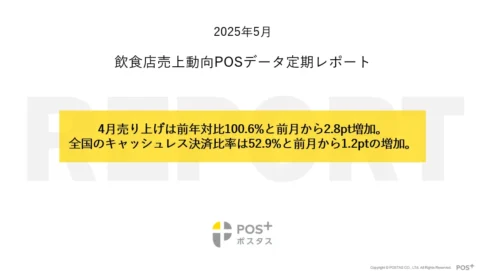




コメントを残す