飲食業界は変化が激しく、近年はコロナ禍による売上減少、スタッフ不足、原材料の高騰、デジタル化対応など、さまざまな課題に直面しています。そうした背景の中で、「飲食店向けサポート事業」を展開する企業の重要性は年々高まっています。
しかし、いくら素晴らしいサービスを提供していても、「営業担当が信頼されない」と契約には結びつきません。とくに飲食店オーナーは日々の業務に追われる中で、冷やかしや強引な営業には非常に敏感です。そのため、“信頼される営業” になるためのコミュニケーション術は、事業の成否を分ける最重要スキルと言っても過言ではありません。
本記事では、飲食店向けサポート事業に携わる経営者や営業マネージャーの方々に向けて、現場で実践できる「信頼されるコミュニケーション術」をお伝えします。
1. 「売り込む」より「聞く」が先
飲食店の経営者に対して、最初から商品・サービスを売り込むのはNGです。彼らは忙しい中で営業を受けているケースがほとんど。まず大事なのは、「この人はちゃんと話を聞いてくれる人だ」と思ってもらうこと。
具体的には、以下のような聞き方が効果的です:
- 「今、一番困っていることは何ですか?」
- 「どんなサービスがあったら助かると感じますか?」
- 「過去に他社とトラブルになったことってありますか?」
課題のヒアリングを徹底することで、相手のニーズを引き出すことができ、それに合わせて提案する姿勢が『この人は信頼できる』という評価につながります。
2. 専門家としての情報提供を惜しまない
信頼を得る営業パーソンは、「自社サービスの売り手」である以上に、「飲食店経営の知見を持ったアドバイザー」として振る舞っています。
たとえば、
- 「最近◯◯区では外国人観光客が増えている影響で、英語メニューの導入が効果的です」
- 「LINE予約導入で月間◯件の予約増に成功した事例があります」
など、他店の成功事例や最新の業界トレンドを伝えることで、営業の場が「提案」ではなく「相談の場」に変わります。
“教えてくれる人”は信頼されます。“売り込む人”は警戒されます。
3. 言葉より「表情・態度」が伝わる
飲食店の現場は対面での感情のやり取りが基本です。そのため、営業も「雰囲気」や「信頼感」が非常に重視されます。ここで重要になるのが、「表情」「姿勢」「声のトーン」。
例えば、
- 話すときは相手の目を見る(にらまない)
- 少しゆっくり話す(焦っている印象を与えない)
- 店の外に出た後も軽く一礼する(小さな誠実さが後を引く)
このような細かい所作が「ちゃんとしてるな」「感じがいいな」と印象に残り、競合との差別化になります。
4. 飲食店オーナーの時間軸を尊重する
飲食店の営業時間中に長時間話し込んだり、ランチやディナータイム前に訪問したりするのは、相手の業務を妨げる行為になります。
信頼を得たいなら、相手の「忙しさ」をリスペクトすること。事前にアポイントを取り、5〜10分で済ませることを伝えた上で訪問するのが理想です。
また、「忙しいときにすみません」とひとこと添えるだけでも、相手の心理的な負担は軽減されます。
5. 約束を守る=信頼の基礎
「来週までに資料をお送りします」と言ったのに送ってこない、「今度提案書を持ってきます」と言ったのに来ない——このような小さな不誠実が積み重なると、どれだけ良いサービスでも“信用ゼロ”になります。
逆に、「小さな約束を守り続ける」ことこそが、信頼構築の最大の武器です。どんなに忙しくても、約束したことは即座に実行。守れない場合は、その理由を明確に伝えることが誠実さの証明になります。
6. アフターフォローの一言が“次”につながる
契約に至らなかった商談でも、以下のようなフォローアップが効果的です。
- 「先日お話した件、気になっている点などありましたか?」
- 「新しい補助金制度が出たので、またご連絡しますね」
- 「他の飲食店さんでも〇〇の悩みが増えているようです」
このように、「売る」よりも「気にかける」スタンスが、長期的な関係構築には不可欠です。
まとめ|飲食店向けサポート営業の本質は“信頼構築”
飲食店向けのサポート事業において、営業の役割は単なる契約取得ではありません。お店の未来を共に考え、より良い選択肢を提示できる“信頼できるパートナー”になることが、最大の使命です。
そのためには、商品知識や営業力よりもまず、**「信頼される人間力=コミュニケーション術」**を高めていくことが大切です。
今日からでも実践できることはたくさんあります。ぜひ現場で一つずつ積み重ね、あなたのサービスが飲食店の未来を支える存在となることを願っています。


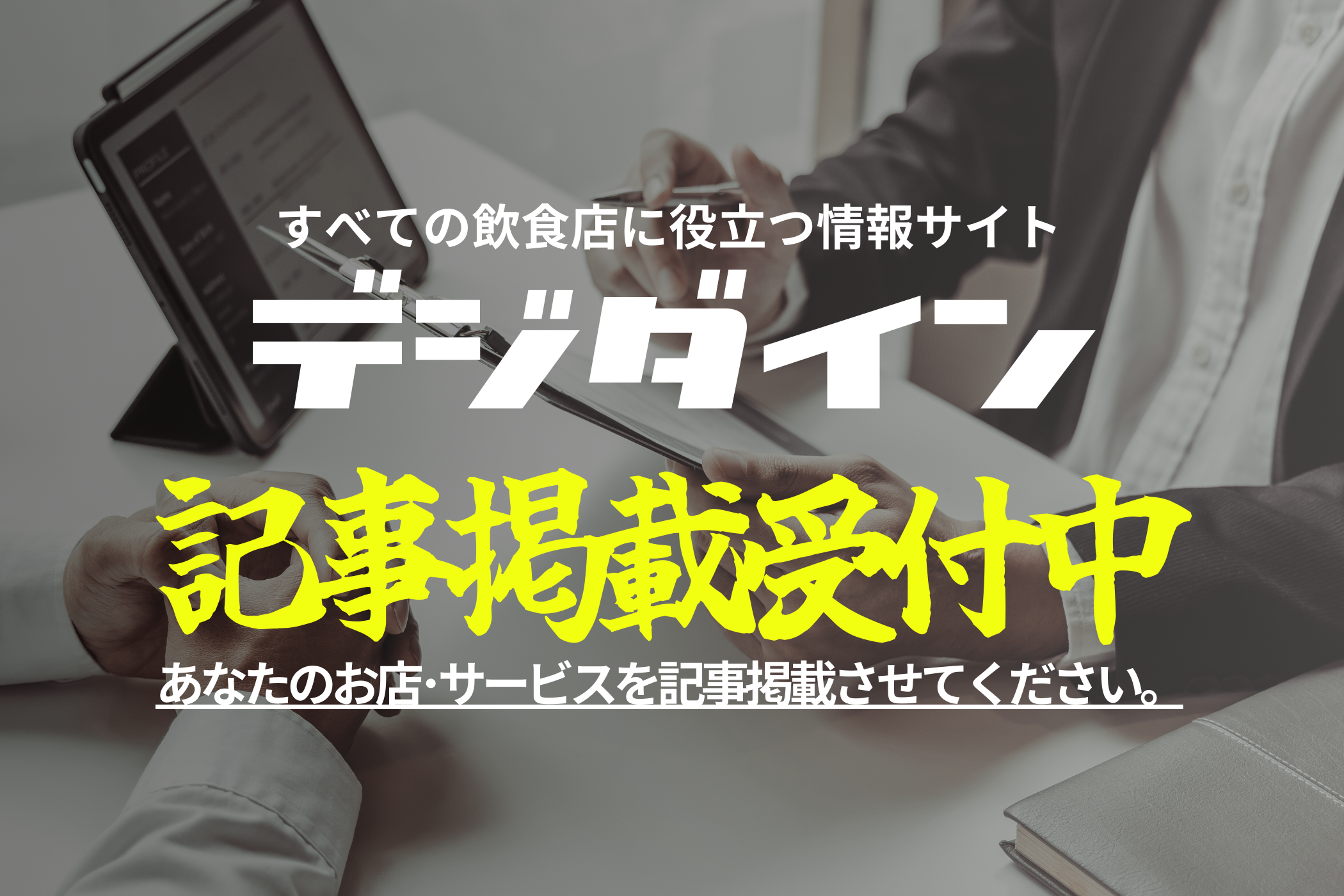
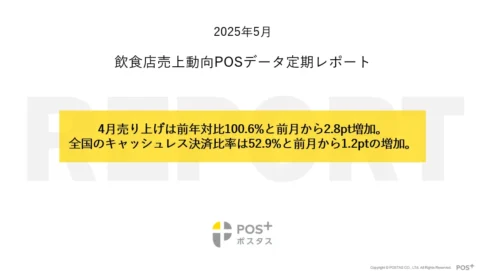




コメントを残す