はじめに:賞味期限管理の重要性
飲食店において、食材の賞味期限管理は利益率の向上や衛生管理の強化に直結します。適切な管理を行うことで、フードロスを削減し、コストパフォーマンスを最大化できます。本記事では、飲食店経営者の方に向けて、賞味期限管理の具体的な方法と効率的な食材管理のポイントを解説します。
1. 賞味期限と消費期限の違いを理解する
まず、賞味期限と消費期限の違いを理解することが重要です。
- 賞味期限:適切な保存方法で「美味しく食べられる」期限。期限を過ぎてもすぐに食べられなくなるわけではありません。
- 消費期限:安全に食べられる期限。期限を過ぎたものは食中毒のリスクがあるため、使用を避けるべきです。
飲食店では、特に消費期限を意識して管理する必要があります。
2. 賞味期限を管理する5つの基本ルール
① 先入れ先出し(FIFO)を徹底する
「FIFO(First In, First Out)」は、入荷した順に食材を使う方法です。
- 仕入れた食材を冷蔵庫やストック棚の奥に入れ、古いものを手前に配置
- 使うときは手前から取り、古いものを優先的に使用する
- 賞味期限の短い食材は視認しやすい場所に配置する
② ラベルを活用して日付管理
賞味期限管理を徹底するために、ラベルを活用しましょう。
- 仕入れた日と賞味期限を明記したシールを貼る
- 色分けしたラベルを使い、期限の近いものを強調する
- デジタル管理ツール(スマホアプリやPOSシステム)を活用するのも効果的
③ 適正な仕入れ量を把握する
仕入れ過ぎは食品ロスの原因になります。
- 売れ筋メニューの食材使用量を分析し、適切な仕入れ量を決定
- 週ごとの売上データを参考にして、仕入れの調整を行う
- 天候やイベントなどの影響も考慮して仕入れ量を調整する
④ 適切な保存方法を徹底する
保存方法によって賞味期限は大きく変わります。
- 冷蔵:5℃以下で保存し、温度管理を徹底
- 冷凍:-18℃以下で保存し、急速冷凍を活用
- 乾燥食品:湿気を避け、密閉容器で保存
保存状態を定期的にチェックし、異常があれば早急に対処しましょう。
⑤ 在庫管理をデジタル化する
手書きやエクセル管理では見落としが発生しやすいため、在庫管理アプリやPOSシステムを導入すると便利です。
- 仕入れや使用状況をリアルタイムで管理
- 期限切れ食材のアラート機能を活用
- 在庫と売上のデータを連携し、仕入れの最適化を図る
3. フードロス削減のための工夫
① メニューの工夫
賞味期限の近い食材を無駄にしないために、柔軟なメニュー運用が重要です。
- 仕入れ状況に応じた「日替わりメニュー」を提供
- 消費期限が近い食材を活用した「期間限定メニュー」の導入
- スープやカレーなど、余った食材を活かせるメニューの活用
② 余剰食材の再利用
食材を無駄にしないための活用方法を考えましょう。
- 野菜の切れ端はスープの出汁に活用
- パンの耳はクルトンやラスクにアレンジ
- 余ったご飯はチャーハンやおにぎりに転用
③ フードシェアリングの活用
食品ロスを減らすために、フードシェアリングサービスを活用するのも手です。
- TABETE(タベテ):売れ残り食材をお得な価格で提供
- Reduce GO(リデュースゴー):飲食店の余剰食材を格安販売
地域のフードバンクと提携し、余った食材を寄付するのも社会貢献につながります。
4. スタッフ教育と賞味期限チェックの徹底
① 賞味期限チェックを習慣化
毎日のルーチンワークとして、スタッフに賞味期限チェックを徹底させましょう。
- 開店前・閉店後の2回、在庫チェックを実施
- 賞味期限が近い食材をリスト化し、優先的に使用する
- 廃棄が発生した場合は記録し、原因を分析
② スタッフ教育の強化
スタッフが賞味期限管理を意識できるよう、研修を実施しましょう。
- 新人研修で賞味期限管理の基本を指導
- 定期的なミーティングで食品管理の重要性を共有
- ベテランスタッフによる監督・指導の体制を整える
まとめ:賞味期限管理で飲食店の経営を強化しよう!
賞味期限の管理を適切に行うことで、
- フードロスの削減
- コストの最適化
- 衛生管理の強化
- 顧客満足度の向上
につながります。
「先入れ先出し」「ラベル管理」「適正な仕入れ」「保存方法の徹底」「在庫のデジタル化」を実践し、効率的な運営を目指しましょう。さらに、フードロス対策を行うことで、利益率向上だけでなく、社会的責任も果たせる経営が可能となります。
今日から実践し、飲食店の経営をより強固なものにしましょう!


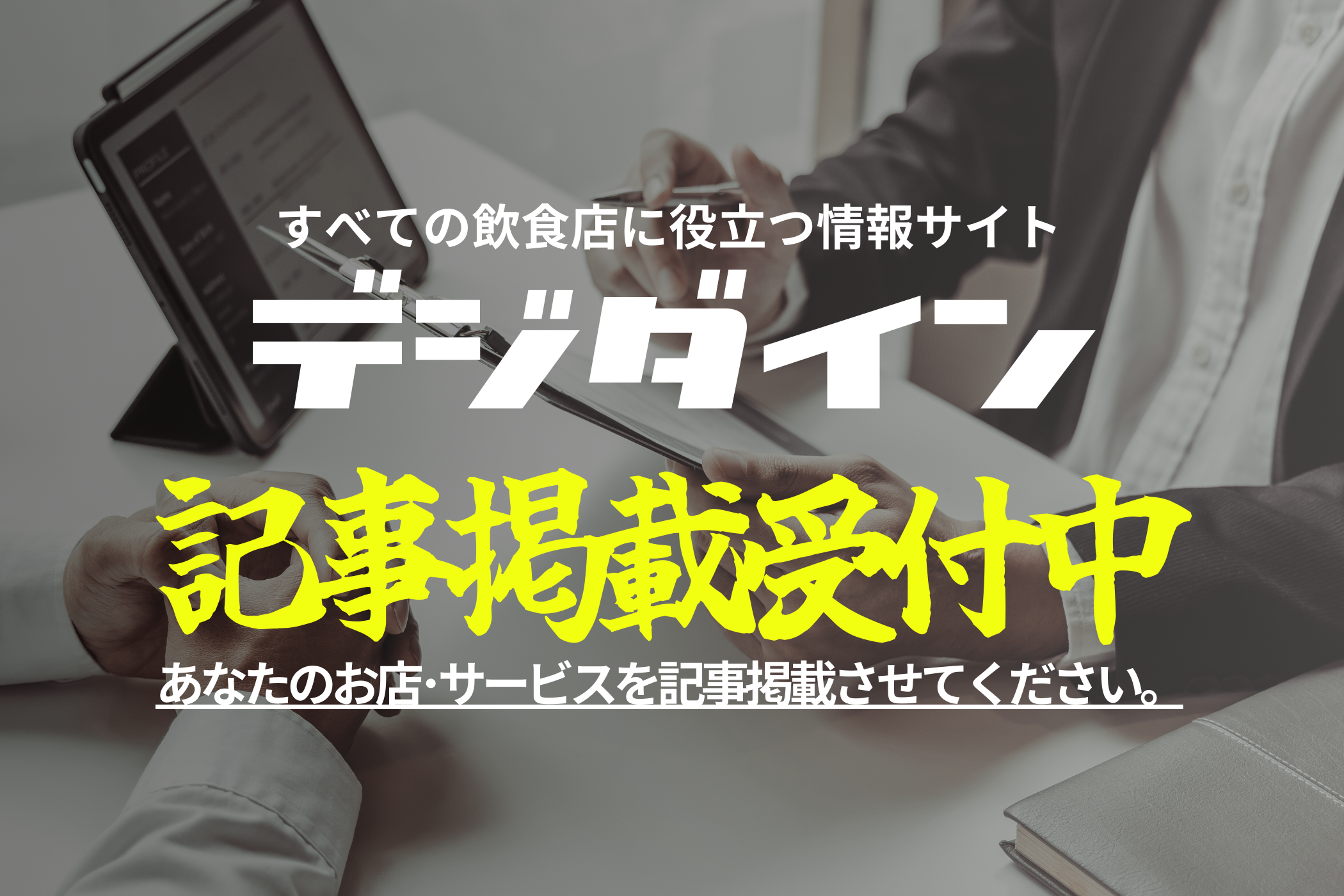
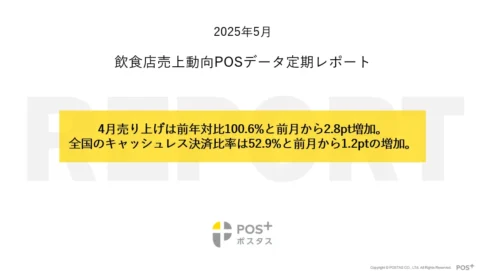




コメントを残す